2018年12月26日公開
2025年03月05日更新
シオデとタチシオデの違いは?食べ方・採り方・レシピを紹介!
シオデという植物を知っていますか?シオデという植物は、山のアスパラガスとも言われている植物となっており、希少な山菜であるとも言われています。今回の記事では、シオデという植物の時期や採り方、下処理の仕方などについて詳しく紹介していきます。似ているタチシオデとの違いや効能、おいしい食べ方のレシピ、そして保存方法などを紹介していきますので、シオデという植物を知っていたという方も知らなかった方も、似ている植物との違いなどをチェックしてみてください。

目次
シオデは食べ方が豊富で効能豊かな山菜
皆さんは、「シオデ」という食材を知っていますか?シオデというのは、食べ方が豊富で、効能豊かな山菜の事となっています。今回の記事では、シオデという食材がどのような物なのか、そしてどのような効能を持っており、どのようなレシピで楽しむことができる食材なのかをチェックしていきましょう。保存方法や時期、そして採り方や下処理などの方法も紹介していきます。
シオデは山のアスパラガスとも呼ばれる
シオデという食材の事は皆さん知っていますか?あまり山菜に詳しくない人ですと、シオデという名前を聞いた事が無いという方も多いかもしれません。シオデというのは山菜の一種であり、「山のアスパラガス」と呼ばれている山菜となっています。なぜシオデが山のアスパラガスと呼ばれているのかというと、芽だしから伸び始めた姿や食感がまるでアスパラガスのようだったからだそうです。それでは効能を見ていきましょう。
それでは、山のアスパラガスとも呼ばれているシオデの、効能についてチェックしていきましょう。シオデという山菜は昔は漢方にも使用されてきたという植物なのだそうで、栄養価も高いといわれている山菜となっていますので効能も期待することができます。漢方では、シオデの茎の部分を粉にした物は、鎮痛作用という効能を期待することが出来るのだそうです。どのような効能があるのでしょうか?
また、シオデは先の方の若い芽の部分を食べますので、ビタミンCや食物繊維が豊富に含まれている食材であるといえます。ビタミンCに期待できる効能は、疲労回復や、美肌効果などが期待できます。また、食物繊維には庁の調子を整えて、便秘解消といった効能を期待することができます。シオデは希少な山菜となっていますので定期的にとるのは難しいかもしれませんが、これらの効能を期待することができます。
希少なおいしい山菜の一つ
山のアスパラガスとも言われているシオデですが、秋田県の方では「ヒデコ」と呼ばれて親しまれてもいるのだそうです。そんなシオデは、発生量が少ないことから、実は希少な美味しい山菜の一つとなっています。この記事では、そんな希少な山菜であるシオデの採り方や、下処理の方法などについても紹介していきますので、早速チェックしていきましょう。
シオデとタチシオデは同じ!他に似た植物は?
タチシオデはシオデの呼び名の一つ
シオデとよく似た名前の山菜に、「タチシオデ」という名前の山菜もあります。タチシオデとシオデとの違いが何なのかというと、実はタチシオデという山菜は、シオデの呼び名の一つとなっており、名前に違いはあれど同じ植物の事を指します。しかし、シオデの方は茎に浅い稜があってざらついたものであるのに対し、タチシオデの茎はそれと違い滑らかになっている、という違いもあります。
タチシオデの特徴として、芽のころに「立ち上がる」という事が記載されていたりもするそうなのですが、これが違いなのかというとシオデも、タチシオデも同様にまっすぐに立ち上がるそうですので、実は芽のころにシオデか、タチシオデか違いを見分けるというのは難しいのだそうです。味も全く違いがないのだそうで同じシオデであるシオデとタチシオデとはよく似ているのだそうです。
時期が一緒の山ぶどうの若芽
それでは、シオデによく似た植物には他にどのような物があるのか、その違いを見ていきましょう。まず最初に紹介するシオデとよく似ている植物は、時期がシオデと一緒の山ぶどうの若芽です。こちらの山ぶどうの若芽は、少し酸っぱくて、若芽からはワインの香りを楽しむことができるものとなっているのだそうです。時期が一緒となっていますので、シオデを採った際に一緒に採取したりするそうです。
似たような場所に生えるワラビ
続いて紹介する、シオデとよく似ている山菜は、似たような場合に生えているというワラビです。ワラビは適応能力が高い山菜となっているのだそうで、シオデの採取できる場所にもワラビは混在して生えているのだそうです。背丈の高い草むらのワラビは、茎の太い立派なワラビとなっているのだそうです。シーズン中は、適応能力の高いワラビの採取で賑わうのだそうです。
シオデの採り方や発生時期
それでは、続いてはシオデの採り方や、発生時期などについてチェックしていきましょう。シオデを採るのに適している時期や、見分け方、そして採り方などをチェックしていきます。山に登って、自分でシオデを採取してみたい、または採り方や発生時期などに興味があるという方は是非チェックしてみてください。それでは、まずはシオデを採るのに適している時期について紹介していきます。
採りごろは春先
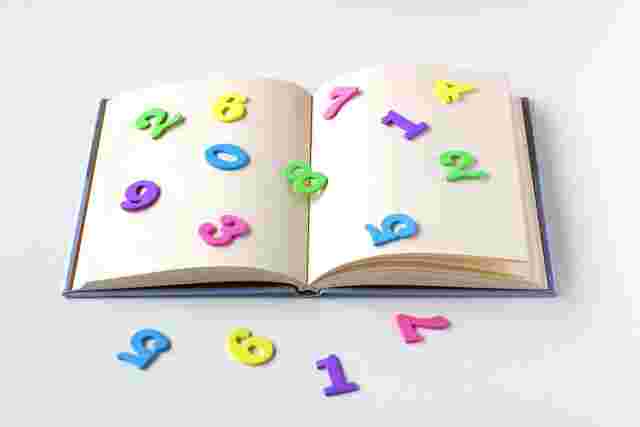
それでは、早速シオデの採りごろ、時期からチェックしていきましょう。シオデの時期は、6月の初旬から中旬ごろとなっており、春ごろが時期となっています。シオデは発生環境が狭いので、採取が難しい山菜となっています。それでは、続いて春ごろが時期となっているシオデの採り方をチェックしていきましょう。シオデを山で見つけるためにはどのような点に気を付ければよいのかを紹介していきます。
蔦を見分けることが重要
それでは、シオデの採り方を見ていきましょう。シオデは見つけるのが難しく、採取は困難な山菜であるとされています。そんなシオデの上手な採り方とは、いったいどのような物なのでしょうか?シオデにはいくつかの種類がありますが、普通見ることができるシオデは、細い蔦のような物を出しているのだそうです。しかし、どれがシオデの蔦なのかを知っていないと見分けるのが難しいので、しっかりと確認しておいた方が良いでしょう。
群生しないため発見は難しめ

シオデは、比較的日当たりの良いところに生えており発見するのは難しくないように思われるのですが、群生していませんのでたくさん発見するという事は難しいのだそうです。なかなか見つけにくく、数自体も少ない山菜となっているシオデは山菜取りになれている人でも、シオデを採りに行く、という採り方ではなく他の山菜を採りに行ったときに一緒に狙う、という採り方をしているそうです。
シオデの下処理と保存方法
それでは、続いてはシオデの下処理方法と、保存方法についてチェックしていきましょう。下処理や、保存方法について詳しく紹介していきますので、シオデの下処理や保存方法などについて気になるという方は是非チェックしてみてください。それでは、最初にシオデの下処理の方法からチェックしていきましょう。
下処理は湯がいて冷水へ
それでは、まず最初にシオデの下処理の方法からチェックしていきましょう。下処理というと面倒くさいように聞こえてしまいますが、シオデの下処理は特に難しいことがありません。シオデは生では食べることが出来ませんので、さっと下処理を済ませて美味しい食べ方やレシピに活用していきましょう。シオデの下処理は、サッと湯がいて冷水にさらしたら完成となります。これで、シオデのあく抜きをすることが出来ます。
保存の場合も茹でてからがおすすめ

シオデを保存しておきたいという場合にも、茹でてから保存しておくことをおすすめします。先ほどはサッと湯がいてから冷水にさらしておきましたが、保存する場合には茹で上がってから、ポリ袋などにシオデを入れて5%の食塩水を少量保存液としてポリ袋などに入れたら、袋の中の空気をしっかりと抜いた後に口を締め、冷蔵庫で保存しておきます。シオデはすぐに味が落ちてしまうそうですので、保存は短期間にしておきましょう。
シオデのおすすめレシピ
それでは、続いてシオデを使用した、おすすめの食べ方やレシピなどについてチェックしていきましょう。山のアスパラガスとも言われているシオデは、様々な食べ方、色々なレシピに活用することができる山菜でもあります。まず最初に紹介するシオデの食べ方は、シオデのお浸しです。あっさりと楽しむことができるレシピですので、シオデをシンプルに楽しみたいという方におすすめの食べ方となっています。
シオデのお浸し
- シオデ10本
- マヨネーズ小さじ2
- 七味唐辛子適量
- 塩小さじ2
- まず、シオデをサッと水洗いしておきましょう。サッと水洗いしたら、お鍋に水と塩を入れて、火にかけていきます。
- お鍋の中の水が沸騰したら、先ほど水洗いしておいたシオデを入れて2分ほどゆでていきましょう。
- シオデが茹で上がったら、ざるに開けて粗熱を取っておきます。シオデの粗熱が取れたら、よく水気をきっておきましょう。
- 水気をよく切ったら、約5cmほどに切って盛りつけていきます。今回のレシピでは、上にマヨネーズ、七味唐辛子をトッピングして楽しみます。もちろん、さっぱりとした味わいを楽しみたいという方はマヨネーズと七味唐辛子はなくても美味しく楽しむことが出来るようになっています。
シオデの天ぷら
続いて紹介するのは、シオデの天ぷらのレシピです。山のアスパラガスとも言われている山菜のシオデを、てんぷらでサクッと楽しむことができるレシピとなっています。そのまま食べても美味しいですし、お好みで塩をかけて楽しんでも美味しく楽しむことができるレシピとなっています。水で洗ってサッと揚げるだけで簡単にできますので、是非こちらのレシピもチェックしてみてください。
- シオデ適量
- てんぷら粉適量
- 油適量
- まずは、シオデを水でよく洗っておきましょう。
- シオデを水で洗ったら、てんぷら粉を付けていきます。てんぷら粉は、米粉の衣を使用しても美味しく楽しむことが出来るのだそうです。
- てんぷら粉を付けたシオデを、油でサクッと揚げていったら完成となります。出来上がったシオデの天麩羅には、お好みで塩を振って楽しみましょう。
シオデの味噌マヨ和え
それでは、続いてシオデの味噌マヨ和えのレシピを紹介していきます。シオデの味噌マヨ和えは、味噌マヨネーズで和風味に楽しむことができる食べ方となっています。ツナをレシピに使用していますので、ボリュームもたっぷりに楽しむことができる食べ方となっています。味噌マヨネーズで仕上げていますので、ご飯のおかずにもピッタリのレシピとなっています。
- シオデ200g
- マヨネーズ適量
- 味噌小さじ1/2
- ツナ缶1缶
- 塩コショウ適量
- まずは、シオデをよく水洗いしておきましょう。シオデを水洗いしたら、続いて沸騰したお湯で1分から1分半ほどゆでていきます。
- シオデをゆで終わったら、5cmくらいの長さに切っておき、そのまま冷ましておきましょう。
- 続いて、ボウルなどにマヨネーズ、味噌を入れたらよく混ぜておきましょう。
- 味噌とマヨネーズを混ぜた3のボウルに先ほどのシオデを入れたら、油を切っておいたツナ缶のツナを入れてさらに軽く混ぜておきましょう。
- 味を見ながら、マヨネーズと塩、そして胡椒の量を調節したら完成となります。簡単に作ることが出来て、おいしいレシピとなっています。
シオデの砂肝炒め
続いて紹介するシオデを使用した美味しいレシピは、シオデの砂肝炒めです。山のアスパラガスとも言われているシオデをふんだんに使用したという一品になっており、砂肝と合わせていますのでボリューミーに楽しむことができる一品となっています。そのまま楽しむのはもちろんのこと、ご飯のおかずとして楽しんだり、お酒のおつまみとしてもおすすめです。それでは、早速シオデの砂肝炒めのレシピを見ていきましょう。
- シオデ10本くらい
- 砂ぎも100g
- 塩コショウ少々
- にんにくひとかけ
- まず、シオデを水で洗っておきましょう。
- 続いて、洗ったシオデの下の方の硬い部分は切落して、5cmくらいの長さにカットしていきましょう。
- 続いて、砂肝は5ミリくらいの厚さにカットしておき、塩コショウで下味をつけていきましょう。
- 先にニンニク、砂肝を炒めていき、砂肝に火が通ったらシオデを投入していきましょう。シオデの緑色が濃くなって、さわると柔らかいと感じるくらいになったら、塩こしょうで味を整えて完成となります。今回は砂肝を使用しているのですが、お肉は砂肝でなくても違うお肉でも楽しむことができます。
シオデを採って新しい料理に挑戦しよう!
いかがでしたでしょうか?シオデは山のアスパラガスとも言われており、希少な山菜となっています。見つかりにくい上に数も少ないと来ていますので、もしシオデを採れた時や、シオデが手に入ったという時には美味しい食べ方で楽しんでみてはいかがでしょうか?シオデは下処理も簡単な物となっており、お湯でサッと湯がいた後に冷水で冷やすだけというすぐにできるものとなっています。
下処理が簡単になっていますので、すぐ料理に活用することが出来て便利な食材でもあります。和えるだけ、揚げるだけで簡単においしいレシピを楽しむことができますから、シオデが手に入った時には是非色々なレシピにチャレンジしてみてください。他の植物との違いもチェックして、自分で山にシオデを採りにチャレンジしてみるのはいかがでしょうか?












